蝉の声がうるさくなったが、私の耳は美冬ちゃんの言葉を捉えてしまっていた。「どういう意味?」などと聞いてしまったけれど、どういう意味なのか理解しているつもりだ。そういう卑怯さを自分の行為ながら情けなくなる。
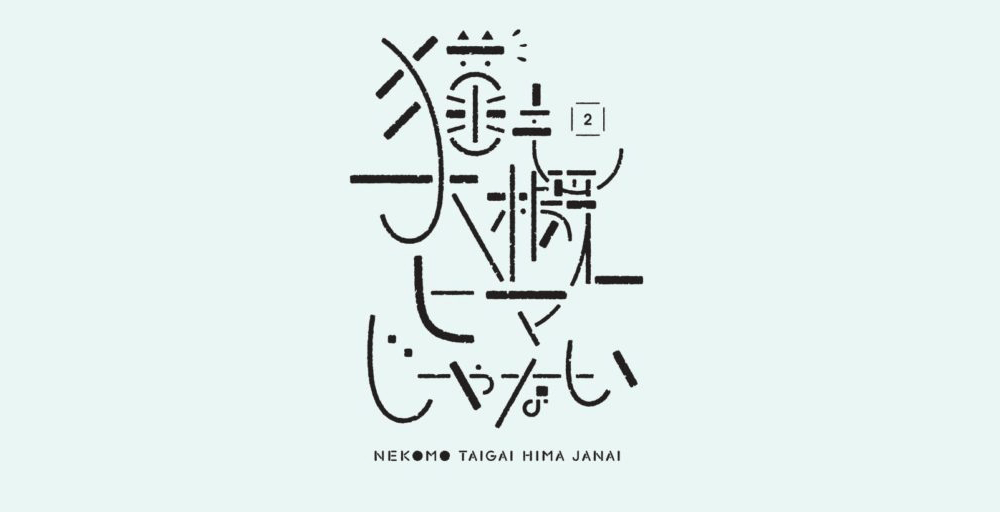
「そのままの意味ですけれど」
私は暫く考えているふりを決め込む。汗が額やら背中を流れ落ちていく。夏という季節は得意じゃない。
「帰りにかき氷でも食べて帰ろうか」
「……ずるいですね。お兄さんって」
「え?」
「ずるいです。ずるいです、ずるいです」
きっとこういう時、明奈は自分の感情を殺していたんだろうなと、そんなことを想像する場合じゃないのに想像してしまう自分がいた。美冬ちゃんの方がどちらかと言えば自分の感情に素直だと思った。
「そうだよ。大人はみんなずるさを覚えていくんだ」
「でも、こういう時までずるくならなくてもいいじゃないですか?」
「なんて言えばいいのさ」
「今すぐ回答が欲しいわけじゃないんです。少しだけ考えてみてもらってもいいですか」
「美冬ちゃんは考えたの?」
「考えました。お姉ちゃんが亡くなって、お兄さんから離婚したって聞いて」
「今日ここで言うって決めてきたんだ」
「はい。朝からずっとそわそわしていました。いえ、昨日からずっとそわそわです」
「でもさ、どうしてこの場所だったのかな?」
美冬ちゃんは墓石に視線をやり、暫く黙っていた。私は彼女の首筋に光る玉の汗を眺めていた。
「だってお姉ちゃんの見ている前でちゃんと伝えたかったんです」
「君は子供だな」
「子供でいいですよ」
もし私が美冬ちゃんの想いを受けてしまったとしたら、明奈、君は驚くだろうか。それとも笑うだろうか。反対は、しないだろうな。でも私には、今の私には彼女の気持ちは素直に受け取ってあげることが出来ないのは分かっていた。きっとそれは彼女もわかっていることなのじゃないか。
「墓参りも出来たし、帰ろうか。かき氷でも食べてさ」
「奢ってくれるんですか?」
「子供に奢るのが大人の役目じゃないか」
美冬ちゃんは麦わら帽子をちょこんと被り、私は水の入った桶を持ち上げて、霊園の出口へと向かった。









