「私からサヨナラって言ってあげようか?」と明奈は言った。その思い出は全く色褪せずに私の中に在り続けた。
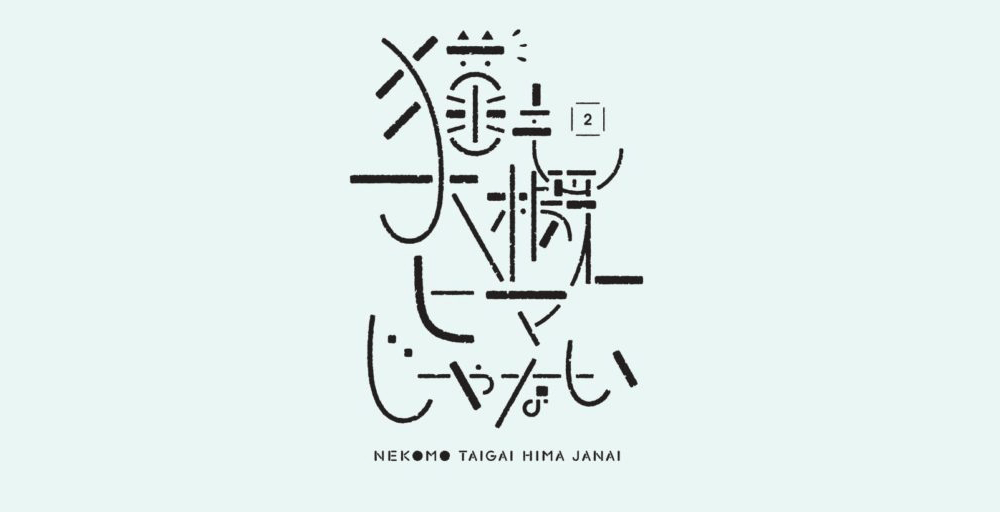
その時、明奈と住んでいた場所は今とは異なるわけだが、彼女はソファに座って窓の外の暗闇を見つめてそう言った。私が別れた妻のことを好きになったのを打ち明けたのを受けての言葉だった。
彼女のことを嫌いになったわけじゃない。他の人も好きになっただけ。だけというのは彼女にとってはそれだけで済むような話じゃない。そのように言わせてしまったことで自己嫌悪に陥った私はただただ黙っていた。何か言わねばと思いつつも言葉が出てこない。出てきたとしてもその言葉で本当に良かったかと自問自答の嵐が吹き荒れることは読めていた。かといってこの沈黙は私がどうのこうのとかではなく、彼女にとっても最悪な時間であることはわかっていた。
「いや、それされるとさ、何か変じゃない」
「じゃあ、どうしたらいい? 私ここで泣いたほうがいいかな。それとも怒ったほうがいいかな」
「冷静に話し合いができればと思って、ね」
「冷静に。私は冷静だよ。つまりはさ、終わりにしようって話だよね」
「終わりというか」
「というか? 相手の人は私のこと知らないんでしょ」
「うん、まあ」
「知られたらまずいんでしょ?」
「そうなるかな」
「で、結婚するならその人なんでしょ」
「そうなるのかな」
「そうなるんでしょ!」
はじめて彼女が殺してきた怒りが私に降り注いだ。きっと彼女は冷静に話を聞いていて、もしかしたらみたいなことを考えた瞬間があっても私に聞いてくることはなかった。たまりにたまったものがその空気を振動させた。
「ごめん」
「そんな言葉聞きたくなかったな」
「ごめん」
「いい。その言葉はもういいから」
「これだけはわかってほしいんだ。自分が明奈のことを嫌いになったとか、好きでない度合いが下がったとかそういうことじゃないってこと」
彼女は黙って私の話を何度も頷きながら聞いていた。聞き終わって彼女はすっと私のことを見据えた。
「違うでしょ。うん、それは違うよ。貴方の中は確実に度合いが変わっているよ。変わらないとは言っていたとしてもね。だってそうでしょ。100で人を愛していたのに、それが2になったらどういう割合になったとしてもそれは割られて50なんだよ。私は50じゃ満足できないんだよ。知ってるのに。私がどういう女か知ってるのに。どうして?」
彼女は僕に悲しそうに聞いてきた。
「どうして私だけじゃダメなの?」










