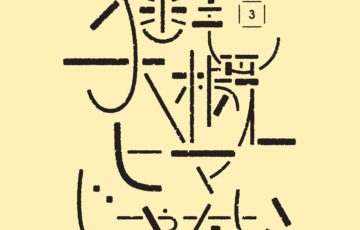「どうして私だけじゃダメなの?」と言った明奈は今、目の前でソファに腰掛け、2時間ドラマの再放送を見ている。のんきなものだ。

「それって面白い?」
「これ? 別に、面白いから見ているわけじゃないわ」
「じゃあ、何で見るの?」
「知ってる? 幽霊ってね、時間だけはたんまりあるの。もう死なないからね」
「そっか」
私は言葉を失った。もう死なないというのをテレビに向けた視線を外すことなくあっけらかんと言い放つ彼女に何を言えようか。
「あ。この人、殺されるわよ」
「え?」
「ほら殺された。お約束的展開すぎてつまらない」
「そう言うなよ。ドラマ作っている人だって、頑張ってるんだよ」
「私ならもっと面白いドラマ書けると思うな。ま、死んでんだけどね」
「あのさ、その死んでる死んでるっていうアピールやめようよ」
「なに、私がそう言う度に苦しい?」
「それもあるけどさ」
「楽になりたいんだね。そろそろ」
「そういうわけじゃないけどさ」
「そういうわけなんだよ、きっと。でもね、私あなたを苦しめるつもりもないんだけど、楽にさせるつもりもないんだよね。うん」
彼女の視線はテレビを見ているようには見えなかった。ただまっすぐ、その薄っぺらいテレビ画面の向こう側、に広がる彼女だけが見えている景色、のようなものを見つめているようだ。千里眼によって何かこれから起こる出来事が見えているのかもしれない。
「君には何が見えているの?」という言葉を飲み込んで、私はそっとテレビの電源を落とした。
「え、ちょっと、見てるんだけど」
「いや、でもさ、これから出かけないとだからさ」
「ああ、もうそんな時間。じゃ、しょうがないね。私はちょろっと妹のところにでも遊びに行ってくるわ」
「そんなふらっと行けちゃうのも不思議だよね」
「行けないのは自分のお墓ぐらいかな。行きたいと思わないし。行ってみた所で私が死んだことを実感するだけだし」
「ほらまた」
「いいじゃない。言うだけなんだから。別に呪うとかしないからさ。あ、もしかして離婚したの、私の呪いかなんかだと思ってたりする? 心外だわ、それは」
「思ってないよ。あれは、自分のせい」
「そ、ならいいけど」
私は玄関に向かい、肩からずり落ちそうになったカバンを掛け直しつつ靴を履いた。夏はまだ終わってはくれそうになく、玄関の扉を開けて一歩出た瞬間に暑さで息苦しさを覚えた。
「行ってらっしゃい」という彼女の声を聞いた気がして、自然と「行ってきます」と返している自分に笑いそうになった。相手は幽霊だぞ。…