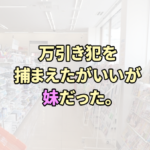いじられるというのはこういうことかと私はタカナシくんの言葉を受けて思った。

「タカナシくんこそ私にとって未知の生き物だわ」
「それはひどいな。僕のどこが未知なのかな。雪男でもないしネッシーでもないよ僕は」
「私はそれほどあなたを知らないっていう意味でよ」
「なるほど。じゃあ、なんでも聞いてくれればいいさ」
そう言われるとすぐには質問が思いつかない。
思いついたと思ったら「ご趣味は?」みたいなセリフで、バカバカしくて口から質問が出ていかなかった。
タカナシくんは私の質問を今か今かと待っていた。憎い笑顔である。
「あ、あれUFOじゃない?」
「え、どこどこ」
UFOなんて飛んではいなかった。私はさも飛んでいるのを見つけてテンション上がっている人間を演じなければならなくなり、それに同調してくれないと私がとてつもなく惨めな気持ちになるわけで。
「ほら、あの山の」
「山のどこ?」
「頂上付近にきらきらって光っている」
光ってなんていない。その時光っていたのは私の額の汗ぐらいだ。
「見えないよ。ほんとにほんと?」
見えるわけがない。いないのだから。
私はタカナシくんの顔を両手で挟んで山の頂上あたりに向けた。
「どう、見える?」
「うーん、あれかなぁ。でもあれ動かないよ。星じゃない?」
「星かぁ。星かぁ」
落胆の声を上げてみせる。私の素人芝居は恥ずかしくも続いていた。
「落ち込まないでよ。あれは星だけどさ、僕はUFOとか信じてる人間だから、いつかは見たいって思うよ。その時はこうやって二階堂さんが居て、『あれ、あれあれ!』とか言って、僕はその時もUFOを見つける事ができなくてさ、『あれだって、ほらぁ』って、こうやって二階堂さんが手でその方向を定めてくれてさ」
「うん」
「定めてくれてさ。……あれ? 何の話だっけ?」
「いつかはUFOが見たいって話でしょ?」
「そうだったそうだった」
「いつか、一緒に見られるといいね、UFO」
「見られるさ、多分」
「ええ」
そっと私は彼の頬から手を離した。うっすらと手の平が汗ばんでいた。これはタカナシくんの汗だろうか。私の汗だろうか。
「で、これからどうする?」
「UMA、見つけるには時間が足りないわね、もう」
私はタカナシくんの向こうに見える夕日を見つめた。タイムリミットだ。
「今日は、もう帰ろう」
「そっかぁ。もう夜になってしまうし、仕方ないか」
「ごめんね。付き合わせておいてクレープを食べて散歩ぐらいしかできなくて」
「いや、いいよ。うん、僕は楽しかったから」
「なら、うん」
私たちは駅に向かって来た道を戻った。
「へぇ、こんな所にペットショップがあるんだ」
とタカナシくんが声を上げてお店に入っていく。
私は遅れてそのあとをついて行った。
お店には店員と一組のカップルがおり、私達の入店をあまり気にはしていない様子だった。こちらとしては冷やかし以外の何物でもないので気にされずに内心ほっとした。
「ねぇ二階堂さん」
「なに?」
「二階堂さんはイヌ派ネコ派と言ったらどっち?」
「それは究極の選択ね」
イヌもネコも飼ったことはないけど、動物の動画を見るのは好きだ。見ている時の私の顔は誰にも見せられないぐらいにニヤけていると思う。
「うーーーーん、ネコ!」
「ネコかぁ。うん、二階堂さんはネコを選ぶと思ったよ」
「どうして? 私イヌも好きよ」
「でも迷った挙句のネコでしょ」
「まあそうだけど」
私の中でイヌへの申し訳ない思いが沸々と湧いてきた。
ごめんよ、イヌ。
「もし飼うとしたら、どのネコがいい?」
「え、えーと、えーとね」
私はペットショップの愛くるしいネコたちに見つめられながら、もし飼うとしたらという1点で妄想しつつお店の中を見て回った。そして暫く悩んだ結果、一匹のネコを選んだ。この子だ、もうこの子しかいない。
「この子、絶対飼うならこの子がいいわ」
「へぇ。アメリカンショートヘアーだって。うわ、意外と高いな、お前」
タカナシくんはしゃがみこんでケースの中のネコに話しかけた。
値札には10万円を超えた金額が書かれていた。高い。
高校生のお小遣いではとてもじゃないけど飼えそうにない。
「じゃあ、チョット待っていてください」
という店員の声がしたかと思うと、まっすぐ私達の方に歩いてきた。
私とタカナシくんは道をゆずるように立つと、店員は私が選んだネコをケースから取り出した。
「そのネコ」
私はつい声を上げてしまっていた。
店員は私のことをちらっと見ると、
「ああ、今あのご夫婦が買われてね」
と言葉を残し、そのご夫婦とやらの待っている場所に戻っていった。
幸せそうなカップルがネコを眺めて楽しそうに、仲睦まじく店員と語らっている。
私は空になったケースを見つめ、ネコの幸せを願った。
「さぁ、帰ろうか」
とタカナシくんは言った。私は頷き、お店を後にした。
前を歩くタカナシくんは何度か後ろを歩く私を気遣うように振り返ったが、私は駅に着くまで一言も言葉を発しなかった。タカナシくんは困った笑顔で私を見たが、今の私には一粒の言葉の欠片すら身体の何処にも見つけることは出来なかった。
ごめんね、タカナシくん。