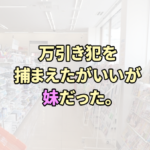放課後、タカナシくんは私の指示に従って帰宅せず教室に残ってくれた。
日直の熊井さんまでが残ったのは予想外だったけど。

「心を開くにはどうすればいいと思う?」
とタカナシくんは言った。
「積極的に話しかける。愛想笑いを浮かべる。相手に合わせる」
と私がすかさず答えると、タカナシくんと熊井さんは同じような顔をしてため息をついた。
失礼な人たちだ。
「それだとなんだか『あなたたちのレベルに合わせてあげてる』感が出ちゃってるのよねぇ」
と熊井さんが腕を組みながら言った。
「そんなつもりはないけれど」
「二階堂さんって、喋っていないだけでちょっと上の人オーラ出してるから」
「気をつける」
「ちなみになんだけど、二階堂さんの親友というか、友達って誰?」
「…友達?」
「そう、友達」
微妙な空気が私達の間に流れた。
「なに、この沈黙は。タカナシくん、こういう時は男なんだから」
「ちがうちがう、え、いま男とか女とか関係ないから」
「逆に聞くけど、あなたたちに友達っているの?」
と聞いた私がバカだった。即答する二人。確かにいま挙がった名前の子と彼らは
とても仲良く休み時間やら過ごしているのを見かけたことがある。
そう言えば私にはそういう人間はいない。
必要と感じたこともなかった。これはとてもまずいことなのか。
「ぼっち感っていうの、そういうの二階堂さんないじゃない。
逆にそれが仇(あだ)となっているんじゃないかなと」
「それあるわよ、二階堂さん!」
「急にテンション上げないでよ」
「ぼっちじゃないイコール心配しなくてもいい存在。
むしろ心配するほうが失礼にあたる存在」
「つまり私に友達が出来るには、心配をかけられるようになればいいと」
「そうそう」
「だからテンション!……でも、そうなると、」
私が言おうとしたことにタカナシくんはいち早く気づいた。
「そうなると、僕たちはもう二階堂さんと友達なんだな、きっと」
ついさっきまではただのクラスメートだった二人が、
そのタカナシくんの言葉によって明らかにさっきとは違って見えた。
どうやら私にも友達が出来たようです。