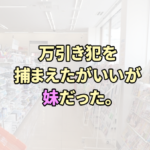問題があったとすればそれは私だったのだろうと妻が置いていったティーカップを迂闊にも落として割りながら思うある日の朝。

こんなことを考えるのはそもそも何回目だろうか。何個割ったのだろうか。
そのような数を数えているほど暇でもない。シンクで割れた元ティーカップを拾い上げながらそれに纏わる思い出について振り返ってみたが何一つ思い出せないのは私の罪なのだろうか。この罪に対してどのような罰があるのだろうか。ゴミ袋に捨てられる欠片を一瞬見つめるも、そっと袋の口を閉じた。
電話が鳴る。出るか出ないかはそれは私の自由意志だがこのまま放置するような性格でもなく、ずっと鳴り続けている電話というのも癪に障るものだ。ご近所迷惑甚だしい。私はそっと受話器をつまみ上げ、耳に押し当てる。
「もしもし」
「あ、すみません、間違えました」
という女性の声を私の右耳に残してその通話は切れた。時刻は7時47分。そっと受話器を元の位置に戻す。まるで受話器は今あったことなど初めからなかったかのように私に語りかける。「何かありましたか、ご主人様」とでも言っているようだが、もちろんそんな言葉を受話器が話すわけもない。
「さて、猫に餌でもやるかな」
と誰に説明しているのかわからないような言葉を実際に口にした私は不図思う。どの猫にだと。
結婚したのを機にペットショップで二人で選んで飼うことに決めた猫、名前は……なんだったか、確か3文字ぐらいだった気がするんだが、すっと出てこない。まあいい。大した問題ではない。
妻が、いや元妻が猫は引き取ったからこの家には「ねこ」の「ね」すら残されてはいない。探せば「ne」の「n」ぐらいは見つかるかもしれないが。あの猫はなんという種類だったのだろうか。電話が鳴る。今度は携帯電話だ。7時52分。朝も早くから何の用だろうかと思いつつも私は4コール目で出る。正確に言うならば4振動目だが。
「もしも」
「あ、私。昨日送ったから」
「何を?」
「離婚届」
「そ」
「そう」
「じゃ、届いたら書いて出しておくよ」
「うん。お願いね」
『もしもし』の『し』まで私に言わせずに言うだけ言って切ったのは元妻。
こうまで冷え込んだ関係になるまでどのぐらいの月日を共にしたのだろうか。数えようとすれば数えられるが私はそこまで暇ではない。
…しかし、『もしも』とはなんだろうか。もしも、もしも…。考えたところで何が出るわけでもない。
さて、と。猫に餌でもやるかな。