何が不満だったのか。俺は万引き犯を目の前にして考えていた。
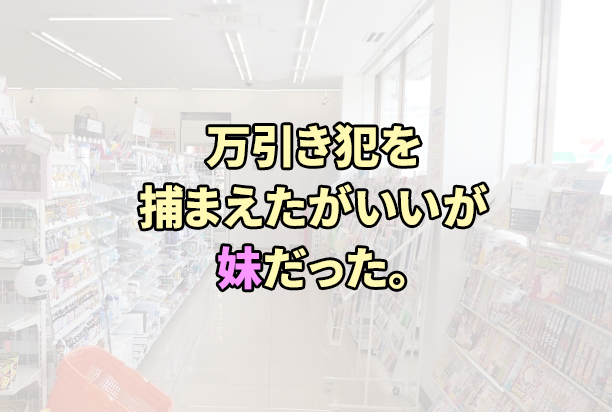
万引きしたものは「レモンティー」「ストレートティー」「ミルクティー」を一本ずつ。何処ぞでティーパーティーでもやるつもりか。ティーパーティーでも。
「何か言ったらどう。さっきから黙ったまんまだけどさ。……ティーパーティーは何処でやるのよ?」
『はぁ? 何言ってんのこのおっさん』という目で見上げられた俺は、ひとまずため息をついた。ちなみに俺はまだおっさんの領域ではない。年齢も体力も。見た目はそうだな、19歳ぐらいだと言っても過言ではない。
レモンティーを持ち上げて、何でこんなものを盗んだのか、改めて考えてみる。彼女が何も言わない以上は考えるしかない。想像して、妄想してみるしかない。よし。
「君はこのティー3種類でパーティーをやろうとしているんだ。同級生とだろう。いや、もしかしたらカレシィ(↗)とかもしれない。まあ、誰であろうと構わないが、そのパーティーにはこのコンビニで盗んだティーが振る舞われる。そして味比べだ。いや、そもそも色で当てられるだろうから目隠しが必要だな。いーや、レモン、ストレート、ミルク。…当てられないわけがない。そうだ、当てられないのは飲んだことがないような人間ぐらいだ。何故違う会社の同じ種類の紅茶にしなかったのか。甚だ疑問だ」
ここまで私は1人で喋りきった。彼女は俯いて何も言わない。だんだん気のせいだとは思ったが、恥ずかしくなった。俺はここで何をしている。何をさせられている。その時、今まで何も反応をしていなかった彼女が微妙に動いた。そう微妙にだ。ごそごそとポケットをまさぐって何かを取り出した。それはまるで商品棚から持ってきました感漂う『アイマスク』だった。
「そうか。そうか。お利口だな君は。言われる前に出すんだものな。。。アイマスク、これも万引きしたのね」
頷く彼女。
「うちの店、アイマスクなんて置いてたっけ」
と独り言ちた俺は、頭を掻きながら思い返していた。しかし、どう考えても『アイマスク』なんてものを発注したことも、品出ししたこともなかった。
「え、これ、本当にうちの店」
「3丁目のスーパー」
ようやく口を開いたかと思えば他所での罪を認めるような発言。殊勝な事だ。
「あとで返しに行かないと。謝りに行かないとな」
「うん」
「なぁ、もう一つ喋り始めたついでに聞きたいんだけどさ、なんで俺が働いている店で万引きした?」
「知らなかったから。兄さんがバイトしてるコンビニだなんて」
「そうか」
俺は改めて妹を見つめた。そしてデスクの上の3本の紅茶を眺めた。「なんて日だ」なんて言えたら楽になるだろうか。











