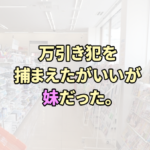芸能マネージャーを始めた頃、この事務所で使っていたのは日産のブルーバードだった。確かあの車種はだいぶ前になくなったと聞く。時代の流れには逆らえないし、その分時間が経過したのだと寂しくも思う。

後部座席でふてくされたような顔をして座っている朱乃をバックミラーで盗み見る。
「さて、と。別に行き先なんてないんだが」
「え、買い物じゃないんですか?」
「どんだけ信じやすいんだよ」
「じゃあ、何しに私たち車に乗ってるんですか?」
「車に乗るために車に乗っている」
「帰りましょう、事務所。私そんなに暇じゃないんですけど」
「そりゃ、俺の方が暇じゃない。何か話すつもりでドライブをしているわけでもないし、俺はお前を諭すつもりもない。ただ勿体無いなって感じたから、それだけはな」
「伝えたかったと」
ブレーキをゆっくり踏み込む。上空に赤信号が見えた。更に向こうには空、雲。いい天気だと言うのに俺は車の中で何をしてるんだか。
ハンドルを人差し指で「こつこつこつ」と一定のリズムで叩く。別にいらだっているわけじゃない。手持ち無沙汰なのだ。
「そう言えば、あの日もこうして事務所に車で行ったんだっけな」
「あの日ですか?」
「朱乃がスカウト待ちしてた日だよ」
「ああ」
「スカウトは結局されなかったけれども、事務所で働くことが出来た。そして今、目の前にチャンスが浮いている。飛びつかなければ他の人がそれをやる。ただそれだけだ。それでいいか?」
ああ、諭すつもりはないとか言いながら俺はそれに近しい言葉を投げている。やめろ俺。そんな言葉が何も意味がないということは十分知っているはずだ。
「ラジオでもつけるかな」と誰に承諾を得るわけでもなく、独り言つ。「やっぱドライブと言ったらTOKYOFMかな」と信号待ちでチューニングしていると、
「偏見ですよ、それは。文化放送でもいいじゃないですか。私AM好きですよ」
「でもこの時間帯だと洒落た音楽も流れてこないぞ」
「いいんです。パーソナリティの喋りが音楽みたいなものですから」
俺は文化放送にチューニングすると、信号が変わった。このまま事務所に帰ったとして、朱乃の答えが変わるはずもないだろう。そんなことは目に見えていた。じゃあ、どうする。
「あの、スーパーに寄ってもらえませんか?」
「スーパー?」
「だって手ぶらじゃ、変じゃないですか。買い物があると言って出てきたのに」
「そりゃまあ。でも社長だってそんなにバカじゃないぞ」
「でもいいんです。水でもいいから買って帰りましょう。私たちは買い物があって出かけたんですから」
「そのこだわりってなんだろうねぇ」
俺はハンドルを切って右折した。真っすぐ進んだ所に大手の、若干高いお値段で商品を売っているスーパーがある。駐車場に車を滑り込ませ、停車した。朱乃は財布の中身を確認すると、車を降り、スーパーの入口へと歩いていった。俺は降りることなくその姿を見ていた。自動ドア前にやってきて俺が来ないことに、行かないという意思に気づいたのか、朱乃が振り返る。唇が動くが俺には読唇術なんてスキルはない。ただ彼女が言い終えて、唇を閉じ、不意に笑ったその表情を見て迂闊にもこんな感情を抱いてしまったのだ。
「ああ、俺はこいつを売り出したい」
~おしまい~