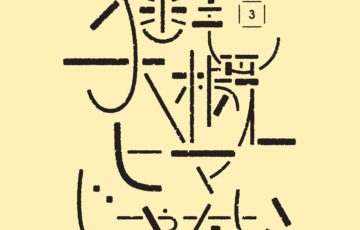「ごめんなさい。二階堂さんが何を言っているのかわかりません」

僕と二階堂さんは期末試験の勉強をすることになり、土曜日学校のある駅から5つ隣の駅にあるカフェに集合した。カバンの中には勿論教科書とノート。
不思議だった。書いたと思っていた僕のノートはまるで新品に近い状態で、むしろ美しかった。そしてそれを見た二階堂さんは、もし彼女がマンガのキャラだったら額におでこに怒りの青筋を浮かび上がらせてみせただろうぐらいには怒っていた。
ひとしきりがみがみと怒られ、授業を受ける態度が良くないなどという話になり、それはあまりに建設的な話ではないよ、と僕が言うと、ようやく彼女はレクチャーを始めた。まずは数学。しかしここで問題が発生した。僕は文系で、数学は端から捨て科目として考えていて、高校に入って以来、赤点しか取ったことがなかったのだ。今更なのだ。そこで僕は言ってしまった。
「ごめんなさい。二階堂さんが何を言っているのかわかりません」
まるでそれは他国の言葉かあるいは最早宇宙人が喋るような言葉にしか聞こえなかった。
「どこがわからない?」
「まず解き方がちっともわからない。何を使えばこの問題は解けるのかな。というかもう数学はいいんじゃないかな。とりあえず四則計算ができれば困らないし」
「国立は目指さないの?」
「国立?」
「大学」
「ああ。進路ね。僕はもともと数学と英語は駄目なんだよね。ひとまず歴史と国語でなんとか」
「そう。私立目指すんだ」
「まあ」
「でも、この時点で捨てるのって間違っている気がする。自分の進路について、選択肢を減らすのは長いスパンで考えると良くないと思うの」
「まあ、一理あるかな。でも出来ないものにこだわっていてもねぇ」
「いいです。わかりました。私に時間を下さい」と突然立ち上がる二階堂さんを見上げる僕。
「え、なに。ひとまず座ろうか」と言っても座らずにいる二階堂さんは僕を見て、
「勉強方法を変えます! 長期的に学力を上げて、タカナシくんが国立に受かるようにします」と拳をわなわなと握りしめて言った。
「ええと、僕はひとまず期末試験を頑張るって話だったような」
「期末試験はひとまず赤点を取らないという消極的な戦略で挑みます」
「それでいいのかな」
「補習さえなければ夏休みを棒に振ることはないってのは調査済だから。あ、ちなみに夏休みの宿題は7月中に終えてもらいます」
「チョット待って。いつも8月の終わりまで片付かないあの宿題を7月中にって、無理だよ」
「無理じゃない」
「無理だって」
「無理だったのはあなた1人だったから。今年の夏には私がいるもの」
もしそれが愛の言葉だったら僕はどれだけどきっとしたことだろう。でも彼女はちっとも恥ずかしそうではない。むしろ言われたこっちが照れそうになる。
ひとまず僕は国立に進む学力を二階堂さんは与えてくれるようだけれど、それに対して僕は彼女に何をあげることができるのだろうか。果たして彼女は何に満足し、微笑んでくれるだろうか。なぁんてことをふと考えてしまった土曜日のお昼前。