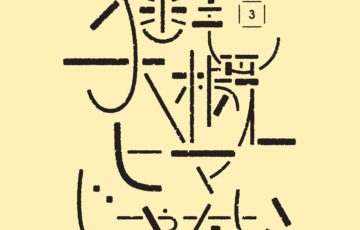ボコボコにされるのが嫌なら金を払えか。嫌な世の中だ、全く。

俺はその男との電話を早々に終わらせ、ひとまず今危機に直面している輪島くんの事務所に連絡をした。「お宅の役者さん、えらいことになってまっせ」と。するとこの業界に長く居るからだろうか、「あ、そうですか。わかりました。こちらで対応します」とだけ言われ、あっさりと電話を切られた。
「終わった終わった」と伸びをしながら報告をすると朱乃も薫子さんもまるで路傍の石でも見るかのような視線を俺に向けてきたが完璧に無視した。
「スイカってもうないんだっけ?」
「知りません。人でなしに上げるスイカなんてもうありません。あるいは食べすぎておなかでも壊して下さい」
「大分な言われようだ」
「オブラートに包んでますけど」
「そんなね、言わんでもいいじゃない。こっちとしてはやるだけのことやったよ。事務所に連絡したらあとはこっちでみたいな対応されたんじゃ、もう俺としてはやることないでしょ。違う?」
「つまらないです。だってですよ。もうこれじゃあ、面白いことに参加すること出来ないじゃないですか?」
「参加させられるの俺だけでしょ。そういう流れだったじゃない」
「その報告を私は楽しみにしていたのに」
「知らないよ。君の楽しみなんて」
「兎に角、あとで事務所に行ってきて下さいよ。どうなったのか目で確認してきて下さい」
「なんで?」
「もしかしたら救えてないかもしれないじゃないですか!」
「救えた救えてないということはもう俺にとっては外の話じゃないか。行ってそれを確認できたからと言って何になる?」
「あ、助けられたんだ、ほっ。ですよ」
「俺は君の『ほっ』のためにわざわざストーカーまがいの行為をしたという俳優の事務所にのこのこ出向けというのか? 徒労だよ」
これ以上朱乃と話しても行き着く所は恐らく『行く』になると思ったので話はこれでおしまいだと言わんばかりに席を立ち、ソファにどさっと腰掛けた。彼女こそここで何をしているんだろうと思わずにはいられない。デビューのためにスカウト待ちして、結果事務所で働かされることになり、あの時の気持ちはもうなくしてしまったのだろうか。
「さてと、仕事の話をしましょう」と唐突に薫子さんが口を開いた。この人はいつだって突然。突然人間だからもう驚かない。俺も朱乃も。
朱乃はスイカの皮が乗っている皿を手に取ると、場を後にした。
「仕事ですか? 誰の何の案件です?」
「若い映画監督さんなんだけどね、キャスティングで連絡もらってて」
「ほう。受けるつもりですか?」
「まあ、ね。彼の才能は認めるところあるし。今のうちに恩を売っておくのもいいかなと」
「で、誰を?」
「それなんだけどさ、朱乃を指名してるのよ」
俺は黙って薫子さんの顔を眺めた。その時、給湯室で水が出る音に混じって朱乃の鼻歌が聞こえてきた。何でプリプリなんだ。