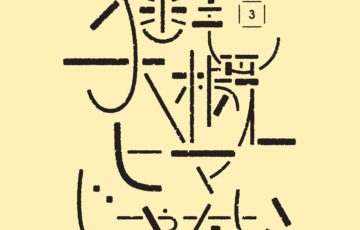美冬ちゃんのビニール傘を持った私は彼女が濡れないようにと傘の位置を探った。
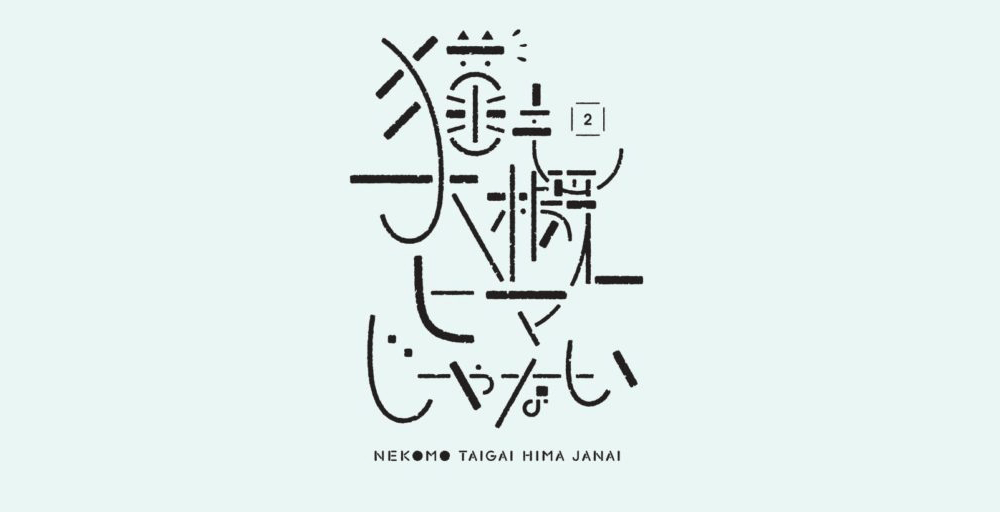
傘を持たないこと、多いんですか?」
「いや、まあ、なくはないさ」
「奥さんに迎えに来てもらえばいいじゃないですか?
ずぶ濡れで帰ってこられて風邪ひいて会社を休まれるよりはいい気がします」
彼女は知らなかった。私と妻が離婚したことを。
いや、ほとんどの人が知らないかもしれない。
『この度、わたくし、小泉晋太郎は妻の美津と離婚致しました』
と言いながら行脚することはない。聞かれれば答えるぐらいだ。
「あのさ、美冬ちゃん」
「なんですか?」
「離婚したんだ」
という事実を私は言葉にした。しかし聞こえるのは雨粒が傘に弾かれる音ばかり。
美冬ちゃんが何か感想を述べることはなかった。
私の右前に位置する彼女の表情は私には見えない。
この沈黙に私は耐えられなかった。
「そうそう。一緒に飼っていた猫さ。あれも妻が引き取っていったよ」
「猫の話は知りません。それよりも離婚したんですか? なんで?」
「なんだろうね。それは私も知りたいんだ」
「離婚の原因がわからない人はきっと次も同じ失敗をします」
「また猫まで連れて行かれちゃうかな」
「笑っている場合じゃないです」
別に笑っていたわけじゃないんだけど年下の女の子に怒られてしまった。
「私、言いましたよね。お兄さんが結婚する時」
「うん」
「別にお姉ちゃんのことは気にしなくてもいいですけど、
ただ選んだその人とちゃんといつまでも幸せに暮らしてくださいね」
「うん」
「うんうんって、覚えてますか?」
「覚えてるよ」
「離婚届に記載している時、少しも私の言葉、思い出せませんでしたか?」
実際、思い出すことはなかった。
あくまでこれは、この離婚は、私と妻との問題だったから。
「ごめん」
「…思い出さなかったんですね、私の言葉。お姉ちゃんのこと」
「ごめん」
「どんな気持ちでお姉ちゃんが身を引いたか、どんな気持ちで生きていたか……」
雨脚が強くなった気がした。
そして美冬ちゃんは雨の中、暗闇の中を、駆けていった。
ビニール傘、濡れに濡れた私の右肩だけが
かろうじて彼女が今まで其処に居たことを現実にしていた。