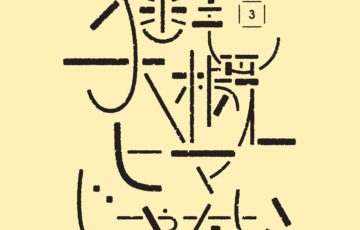雨の中、熊井さんに連れてこられたのは隣の駅のとあるチョコレート屋だった。

「これもらったらいちころよ」とおかしなことを言う熊井さんに対して、僕は苦笑いで手にしたチョコの入った袋を鞄にしまって外へと出た。まだ雨はやまない。
「そうだ、お礼を決めるの手伝ってくれたお礼をしないとだね」
「いいよ。別に私は」
「そういうわけにもいかないでしょ」
「いくよ。私がいいって言ってんだから」
こうなると何も聞いてくれなくなるのが熊井さんだった。
「わかった。じゃあ、喉渇いたんだけど」
「飲めばいいじゃん」
「じゃあ、付き合ってよ」
「だから、私はね」
「いいからいいから」
そう言ってカフェに入ってみたはいいけれど、意外といい値段のするカフェだったことに若干の戸惑いと後悔を抱きながら注文をした。
僕はコーヒーを、熊井さんはバナナジュースを。
「ねえ、聞いてもいいかな?」とジュースを飲みつつ彼女は言う。
「なに?」と僕はコーヒーの黒い水面を眺めながら聞く。暑いのに何でホットを注文してしまったのだろうかと考えつつ。
「タカナシくんは、二階堂さんのことが好きなんだよね?」
驚いた。それは非常に驚くべき言葉だ。
「何でそうなるのかな?」
「何でそうならないのかな?」
「だってさ、え、この前の屋上の続きをやろうってのかい?」
「そんなつもりはないけれど」
「じゃあどういうつもりさ?」
「君は本当に能天気で優しそうな笑顔を浮かべて人を傷つけていくよね」
「何の話だよ」
「いい。わからないなら。っていうか今の君には分かってほしくないから」
コーヒーから視線を窓の外へと逸した時、僕は走り去っていく制服姿の少女を見た。もしあれが二階堂さんだったとしたらと考えると、僕は居ても立ってもいられない気持ちになった。それは熊井さんが指摘する、そういうことなのだろうか。
腰を上げた僕を驚いた表情で見ている熊井さんが窓の外に視線をやる。少女はまだまっすぐと続く道を走っている、その背中が僕らには見えた。
「ねえ、こういう時さ、男はどうしたらいいと思う?」
「さぁ」
「その腰を上げているのが答えなんだよ」
と窓外に視線をやりながら彼女は答えた。それ以上、熊井さんは口を開く気配すらなかった。
「ごめん。お金ここに置いておくよ。足りなかったら明日、請求して」と言って、二千円をテーブルに置くと僕は店を飛び出した。